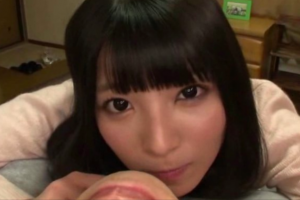「電車よりは、車のほうがいいよ。ぜったい。終電もないし」
枯れるほど泣いた先生は、その目はまだ赤らんでいたけれども、不自然なほどにあっけらかんとしていた。
つきものが落ちた、というやつなのかもしれない。
「僕、免許なんてないですよ」
「なに言ってるの。わたしが運転するに決まってるじゃない」
未だぺたんと座ったままだった彼女は、ふわりと立ち上がった。
「それに、わたしがきみを連れて電車に乗ったりなんかしたら、危ないんだから」
「どうしてですか?」
「だって、その、ほら……いかにも人さらいしてるみたいになっちゃう」
それはちょっと、自意識過剰というものだろう。
先生は確かに綺麗だが、しかし、僕と比べて極端に大人びて見えるというわけではない。
ユウキのほうがよっぽど大人らしいというものだ。
「なんで笑ってるの」
「いえ、別に、そんなことはないですよ」
手ごたえがあった。
この時の僕は、確かに正解の道を選んだという気がしていた。
これからどうしていけばいいのか、なにを言えばいいのか、どこに行けばいいのか。
そんなことは何一つとしてわからなかったけど。
でも、これでいいのだと思った。
間違っていないのだと感じていた。
だって、先生が笑っているのだ。
大したものは持って出なかった。
財布の入ったハンドバッグと数冊の文庫本を右手に抱えた先生は、空いている左人指し指にキーホルダーをひっかけてくるくると回す。
居室を出る直前、僕はもう一度室内を振り返る。
壮観だ。なんとも最悪に壮観だ。いいじゃないか。なんたって僕らは今、ここから逃げ出すのだ。この場所は、悪ければ悪いほどいい。
すがすがしい気持ちの中に、ちくりと、不吉があった。凄惨な部屋の一部、針の山から僕はそれを取り上げる。
「いこう?」
片方だけ靴を履いた先生が、玄関から僕を振り返って呼ぶ。
僕は慌てて、その細長い不吉を、スクールバッグに押し込んだ。
いいさ。今は、考える必要のないものだ。
続きは次のページからご覧ください!!